1日遅れになりましたが、
それでは昨日の雨竜のレポートを![]()
 日陰にまだちょっと雪の残る雨竜町。
日陰にまだちょっと雪の残る雨竜町。
まず向かったのはコチラ! 合同会社幸和。
合同会社幸和。
会社とは言っても農業法人で
実質的には農家さんですね。
さて、改めておさらいですが、
雨竜町での活動テーマは
というコトでまずは米作りの取材ですが、
皆さん米作りの第一歩って、
まず田植えから始まる印象ありません?
でも田植えの時って、稲はもう既に
「苗」の状態になってますよね? ↑こんな感じ。
↑こんな感じ。
ただよく考えたら、稲だって
最初はまず種から芽生えるはず🌱
じゃあ苗になる前に、必ず
「種まき」の作業があるんじゃないの…?
そんなギモンをぶつけたところ、
あまり一般には知られてないけど、
確かに種まきの作業があるということで
そちらを体験取材しに行った次第なのです![]()
 本日ご指導いただくのは、
本日ご指導いただくのは、
JAきたそらち青年部雨竜支部の
岩田祥也さん(右)と金山勇太さん(左)。 では早速ハウスの中へ。
では早速ハウスの中へ。 ハウスの中にあるコチラの機械は
ハウスの中にあるコチラの機械は
「播種機」(はしゅき)と呼ばれるモノ。
「播種」なんて言葉初めて聞いたけど、
要するに「種まき」という意味なのです![]()
 こんな感じの機械。
こんな感じの機械。
今日び稲の種まきは、ほとんど人手は使わず
機械で行われているんだとか![]()
では簡単に流れ説明しますね。 まずはこうして「ポット」と呼ばれる
まずはこうして「ポット」と呼ばれる
穴のたくさん付いた板を積んでいきます。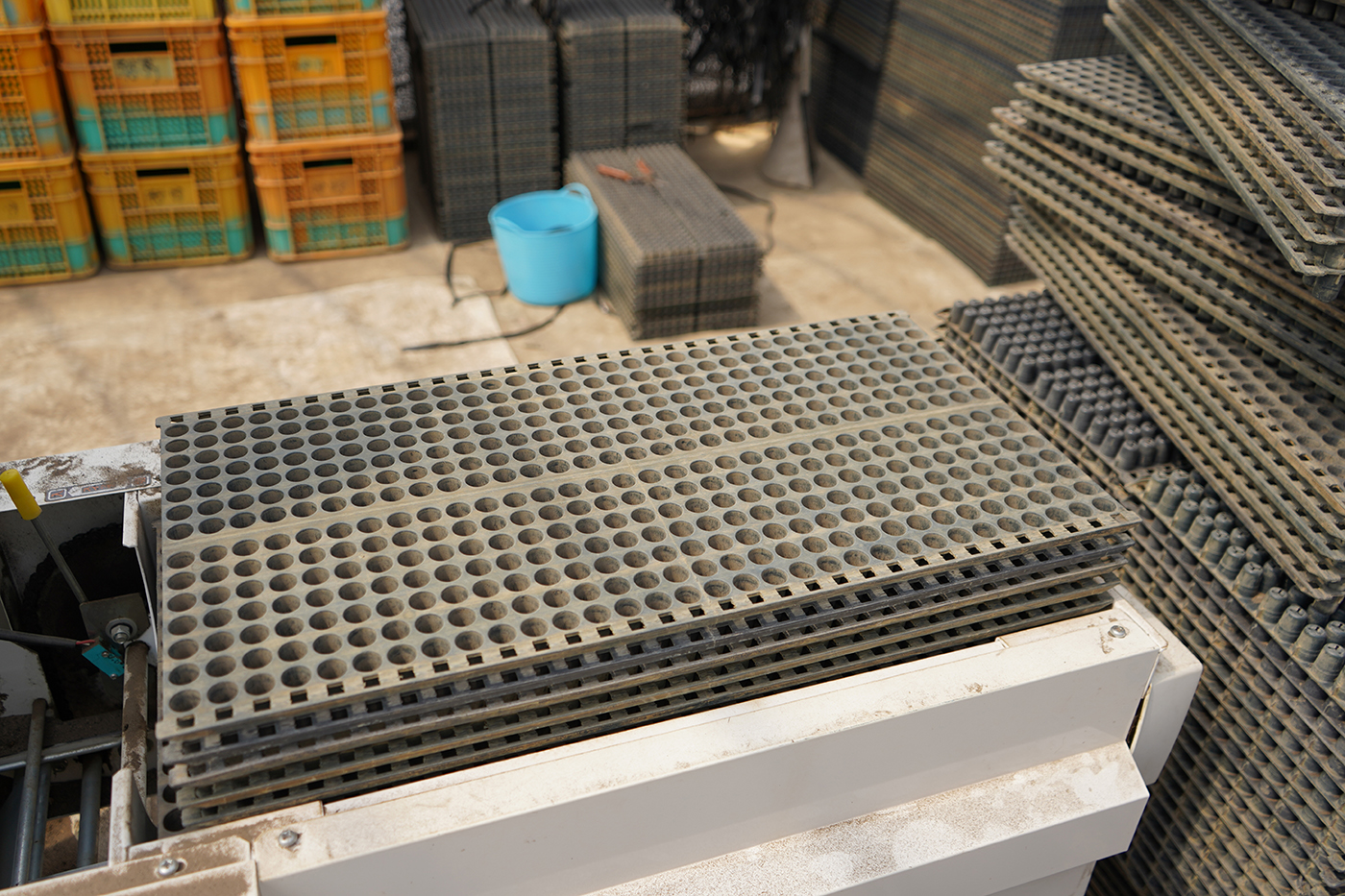 こんな感じ。
こんな感じ。
そこに養分を含んだ土が入っていき… 更に種籾(たねもみ)と呼ばれるお米の種を
更に種籾(たねもみ)と呼ばれるお米の種を
数粒入れていきます。 ↑この種籾を入れていくと…
↑この種籾を入れていくと… こーしてそれぞれの穴の中に、
こーしてそれぞれの穴の中に、
種籾と土が入った状態に。
そしてその上に この覆土(ふくど)と呼ばれる
この覆土(ふくど)と呼ばれる
土を被せていって 機械でならしていくと…
機械でならしていくと… 1枚のポットが完成!
1枚のポットが完成! コレがどんどん積み上がっていきます。
コレがどんどん積み上がっていきます。
ホントは動画の方が伝わるんだけど、
雨竜町地域おこし協力隊の方が
動画を撮ってくれてたんで、
そのうち↓で紹介してくれるかも![]()
(僕のことも時々書いてくれてます![]() )
)
そんなワケで、ほとんど人(熊)手は
必要ないんだけど、
一応作業を体験してみました![]()
 ポット積んで~…
ポット積んで~… 土を補充して~…
土を補充して~… 覆土も補充して~…💦
覆土も補充して~…💦
ほとんど作業のジャマにしか
なってなかったかも…![]()
大変失礼しました![]() 💦
💦
さて、こうして種を仕込んだポットは… こーしてトロッコに積まれて
こーしてトロッコに積まれて
別のハウスへと運ばれて行きます。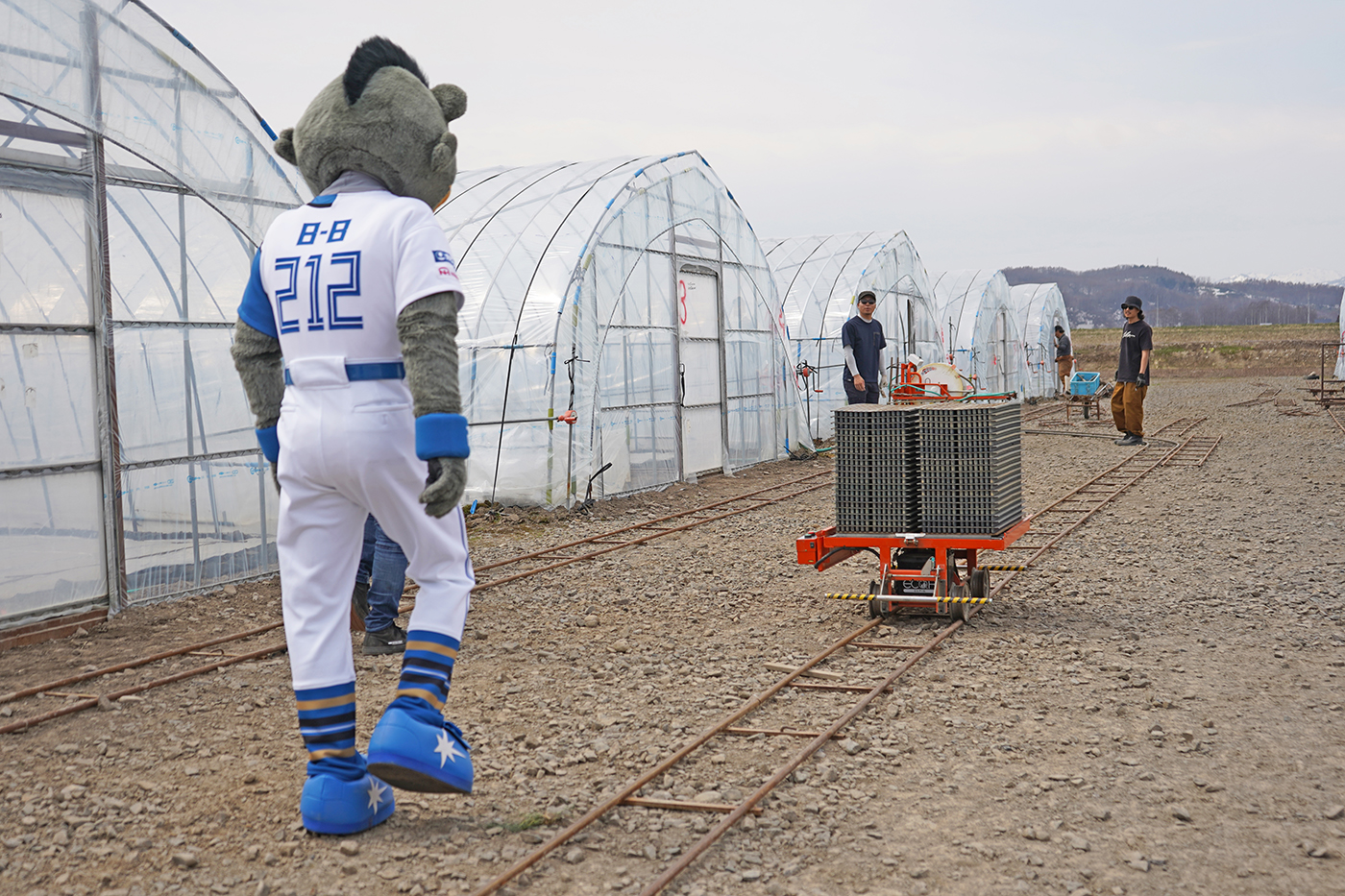 こういうのも全部機械なんですね~…
こういうのも全部機械なんですね~…![]()
そしてコチラが「温床」と呼ばれるハウス↓ ココにさっきのポットを1枚1枚
ココにさっきのポットを1枚1枚
広げて敷いていくのです。
コチラもお手伝いさせていただきました![]()
 この羽みたいに広がってる台の上に乗り…
この羽みたいに広がってる台の上に乗り… ハンドルみたいな道具でポットを掴んで
ハンドルみたいな道具でポットを掴んで
 こうして並べていく。
こうして並べていく。
ココはさすがに手作業みたいですね![]()
 ちょっと曲がったところを直してもらいつつ。
ちょっと曲がったところを直してもらいつつ。 1列が終わると台を前に移動させて…
1列が終わると台を前に移動させて…
 同じ作業の繰り返し。
同じ作業の繰り返し。
奥行き約50mのこの温床。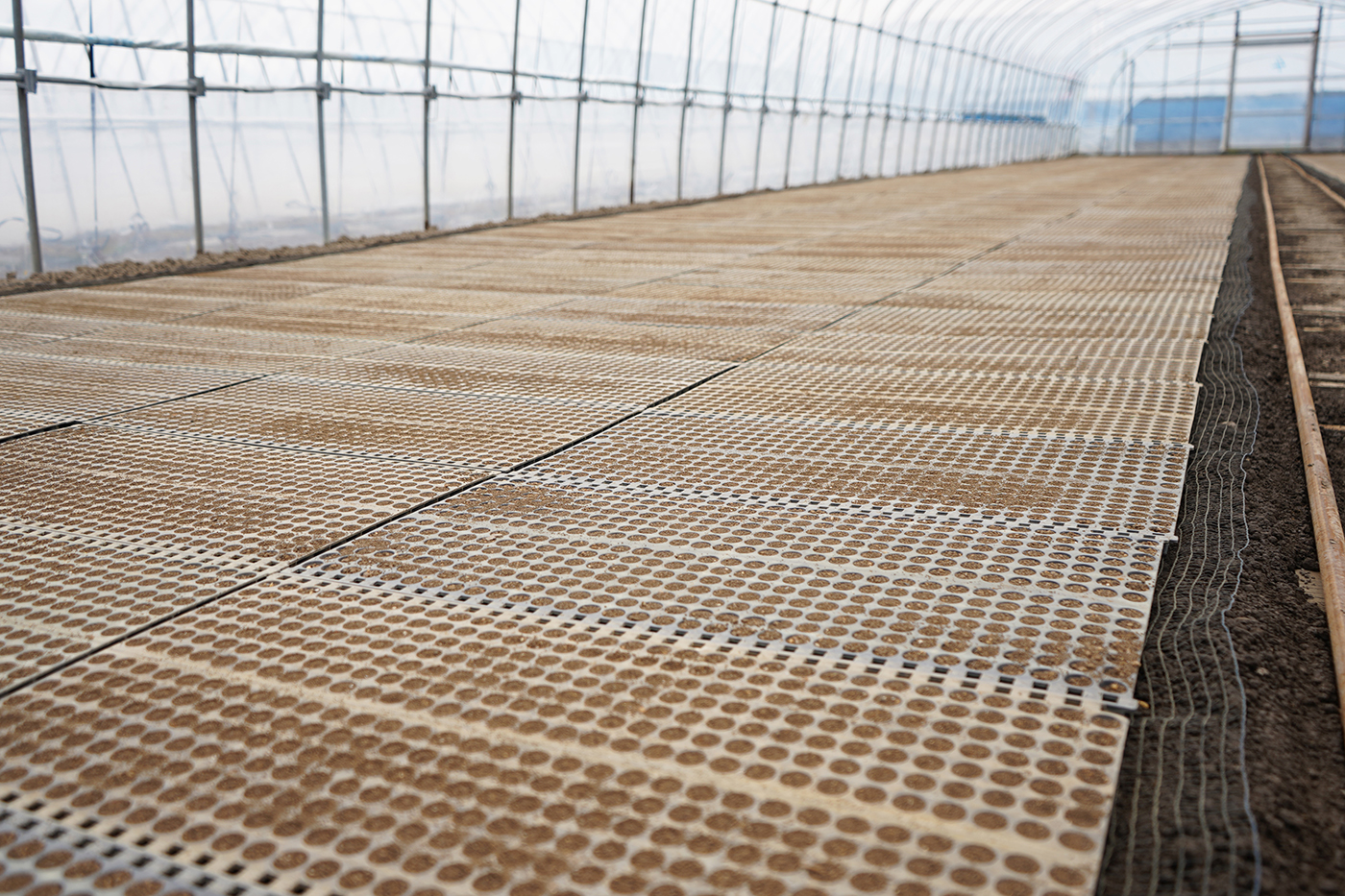 1つのハウスには
1つのハウスには
約1,200枚のポットが並べられるそうです。
ココにはハウスが12棟あるらしいから、
合計で1,200×12=14,400枚くらいの
ポットが並べられる計算になりますね![]()
こうして並べられたポットは
↓みたいな散水機で水をもらったりしながら 芽が出て苗に成長するまで25~30日程度、
芽が出て苗に成長するまで25~30日程度、
このハウスの中で育てられるのです🌱
いかがでしたでしょーか?
田植え前のこういう作業って、
自分で農家してないと
なかなか見れない貴重な体験ですよね。
勉強になるな~![]()
![]()
…と、ここまで体験した後で
「そう言えば田んぼの方はどう準備してるの?」
という新たなギモンが湧きまして![]()
この後急遽、田んぼの方に向かいました![]()
その模様はまた明日お伝えしまーす!




