今日の北海道は久々に過ごしやすかったな~![]()
ホント、ここんとこ3週間以上
逃げ場のない暑さが続いてたけど
(北海道はエアコンある所少ないから
30℃くらいの暑さでもかなり堪えるんです…)
オリンピックの閉幕とともに?
夏も終わりに近付きつつあるのかな~…などと
感じた今日の気候でした。
明日は最高気温…20℃いかないかも![]()
さて、今日は浦河の特産品のひとつ、
昆布のお話。
夏に漁が最盛期となる日高昆布。
この時期日高地方を通ると、
沿道で昆布干し作業してる姿をよく見掛けます。
干した昆布がその後どうなるのか
まだ見てなかったので、
今回そちらの様子を見学させていただきました![]()
 訪れたのは東町地区にある作業小屋。
訪れたのは東町地区にある作業小屋。
今回は、昆布漁師の佐藤利明さんに
お話を伺います![]()
 作業小屋の中はこんな感じ。
作業小屋の中はこんな感じ。
山積みされた昆布を相手に、
佐藤さんが1人黙々と作業を繰り返します。
傍らのTVにはオリンピックの飛び込み競技![]()

 昆布の端っこをハサミでチョキチョキしながら
昆布の端っこをハサミでチョキチョキしながら
選別してるように見えるけど… 見てるだけじゃよくわかんないんで
見てるだけじゃよくわかんないんで![]()
詳しくお話を聞きました。
この作業は「選葉(せんぱ)作業」といって、
乾燥させた昆布を等級別に仕分けしてるそうな。
昆布は1等から5等まで等級があるらしく、
それより下の昆布は加工用に回されるそうです。
 仕分け用の箱には「1~6」の数字。
仕分け用の箱には「1~6」の数字。
これが等級を表すワケですね![]()
実は1等や2等の昆布は市場にほとんど出回らず、
贈答用や懐石料理などの高級料理用に
出荷されるそうです。
一般によく見掛けるのは3等以下の昆布で、
ここにある昆布も3等が一番多いようですね。
ちなみに昆布巻に使われるのは
薄く、早く煮えて柔らかくなる4等の昆布。
おにぎりの具なんかに使われるのは5等、など
用途によって使い分けされてます![]()
じゃあどうやって等級を見分けるのかというと、
主に「重さ」が基準らしいですが、
他にも厚さとか光沢とか、
実に様々な基準があるみたいですよ↓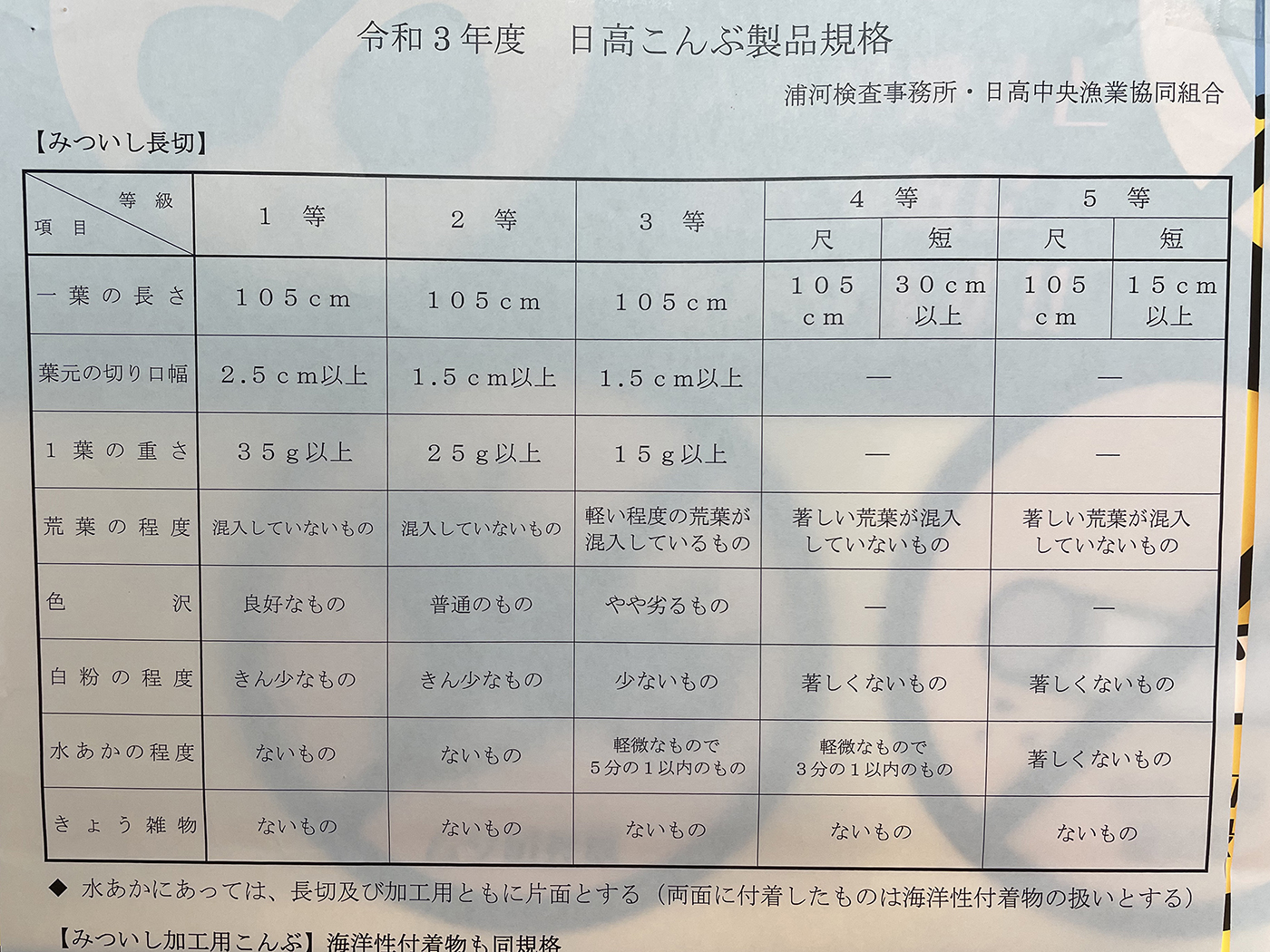 例えば色の良し悪しは黒さで決まったり、
例えば色の良し悪しは黒さで決まったり、
端がペラペラだと良くない、とかあるそうで
さっき佐藤さんが端っこにハサミを入れてたのも
少しでも品物を良くする作業だったみたいですね。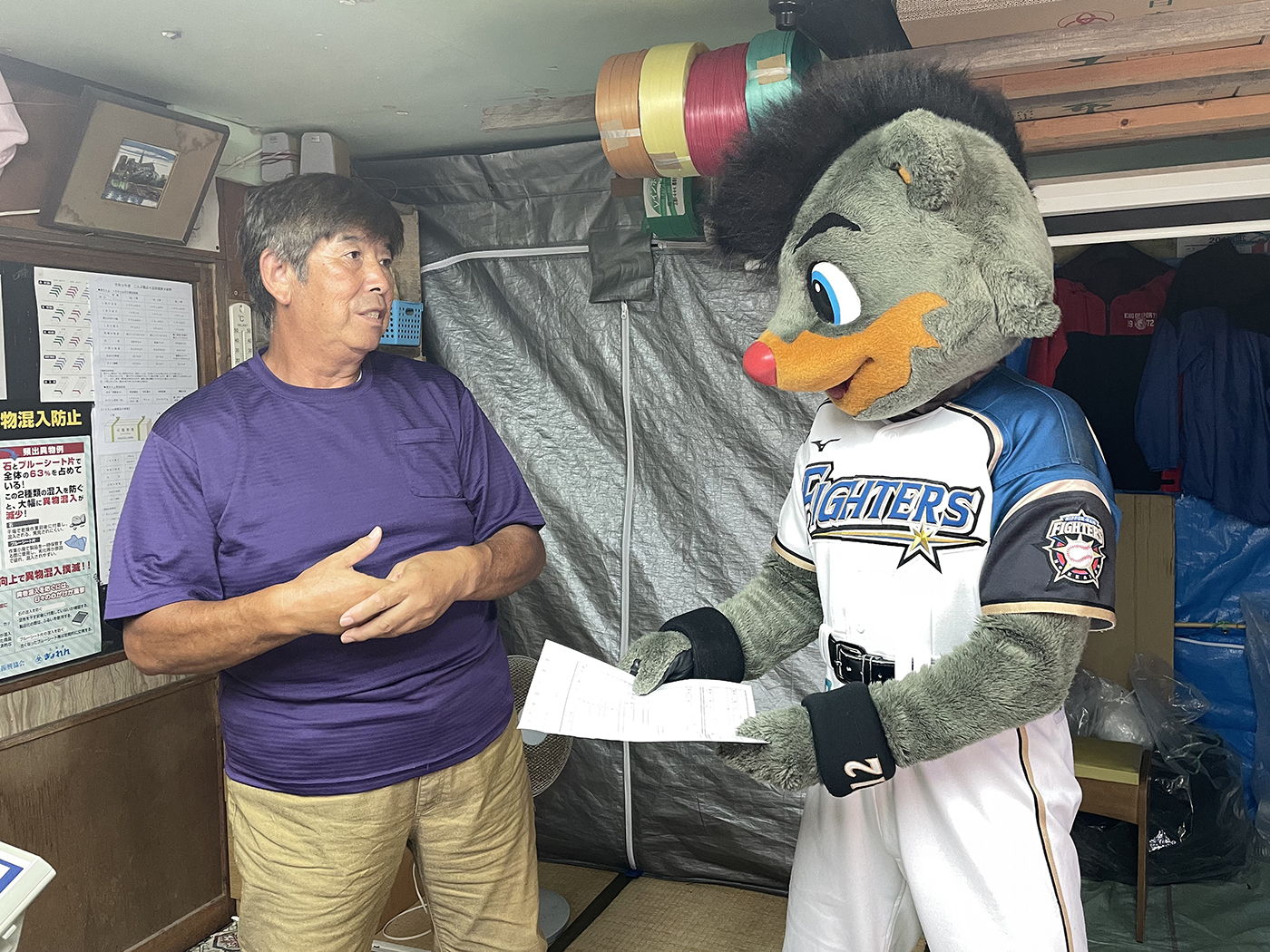 ただ、佐藤さんによると
ただ、佐藤さんによると
この基準はあくまで「人間の判断」で、
言葉で説明するのは難しいらしい。
 僕も実物触りながら見てみたけど、
僕も実物触りながら見てみたけど、
細かい違いはよくわかんない![]()
これってやっぱり…アレですね!
「熟練の技」ってヤツですね![]()
実は佐藤さんもかつては、
コレを体得するまでしばらくかかったそうです。
現在64歳の佐藤さん、
東京で一旦就職後、浦河に戻って
大工さんとして働いてたんですが、
昆布漁師をしていたお父さんが亡くなり、
35歳の時跡を継いで昆布漁師になったそうです。
だけど最初の1~2年はこの選葉作業が全然わからず、
やっと3年目から自分でやるようになったんだとか。
最近は若い昆布漁師もいることはいるけど、
昆布をとることはできても、
この選葉作業という一番難しい作業行程が
なかなか出来ないんで、
なかなか跡取りが現れないということです。
なんか…世界も全然違うし
おこがましいかもしれないんだけど、
そういう職人芸の伝承みたいなの…
スゴく分かる気がするなぁ…。
去年見学させてもらった昆布干しだけど、
ああやって何時間か天日干しした後は
しばらく保管するそうです↓
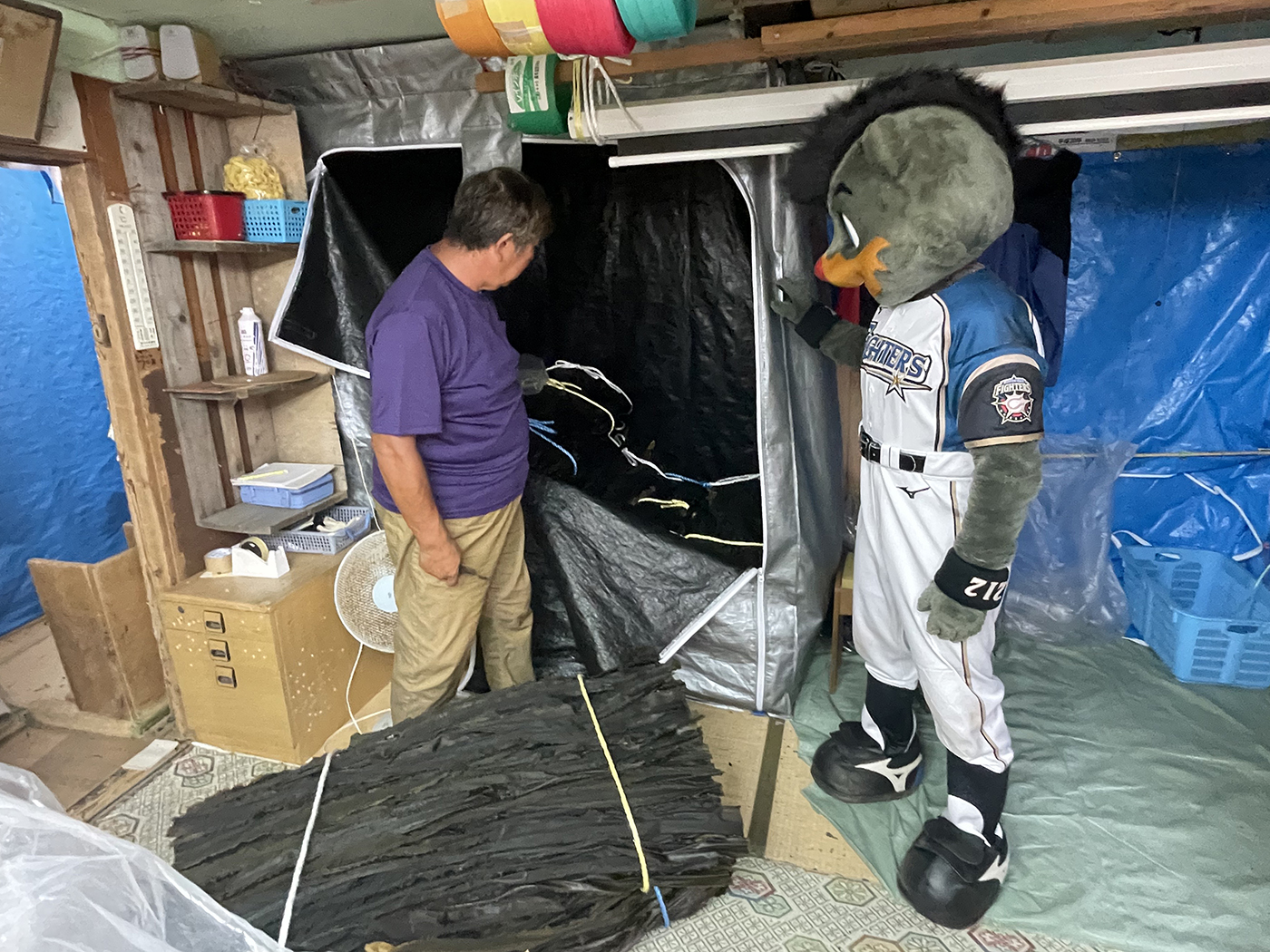 採れたての昆布はまだ青いので
採れたての昆布はまだ青いので
3週間以上寝かせ、その間に
2~3回太陽に当てて乾燥を繰り返して
イイ感じの黒色が出てから
選葉作業に入るんだとか。
船で出掛ける昆布漁は道の条例で
6月中旬~10月中旬と決まってるそうですが、
今年は昆布の収穫が少なめらしいですね![]()
あと、やっぱりコロナの影響もあって
料理で使われる昆布の量が減った関係で
昆布の価格も下がってるらしい。
近年は環境の変化もあって
昆布の収穫が減ってきてて、
昆布漁師の方々も減少してきてるそうです。
取り巻く環境はいろいろ厳しいけど、
ぜひこういう職人さんには
長く元気で頑張ってほしいな![]()
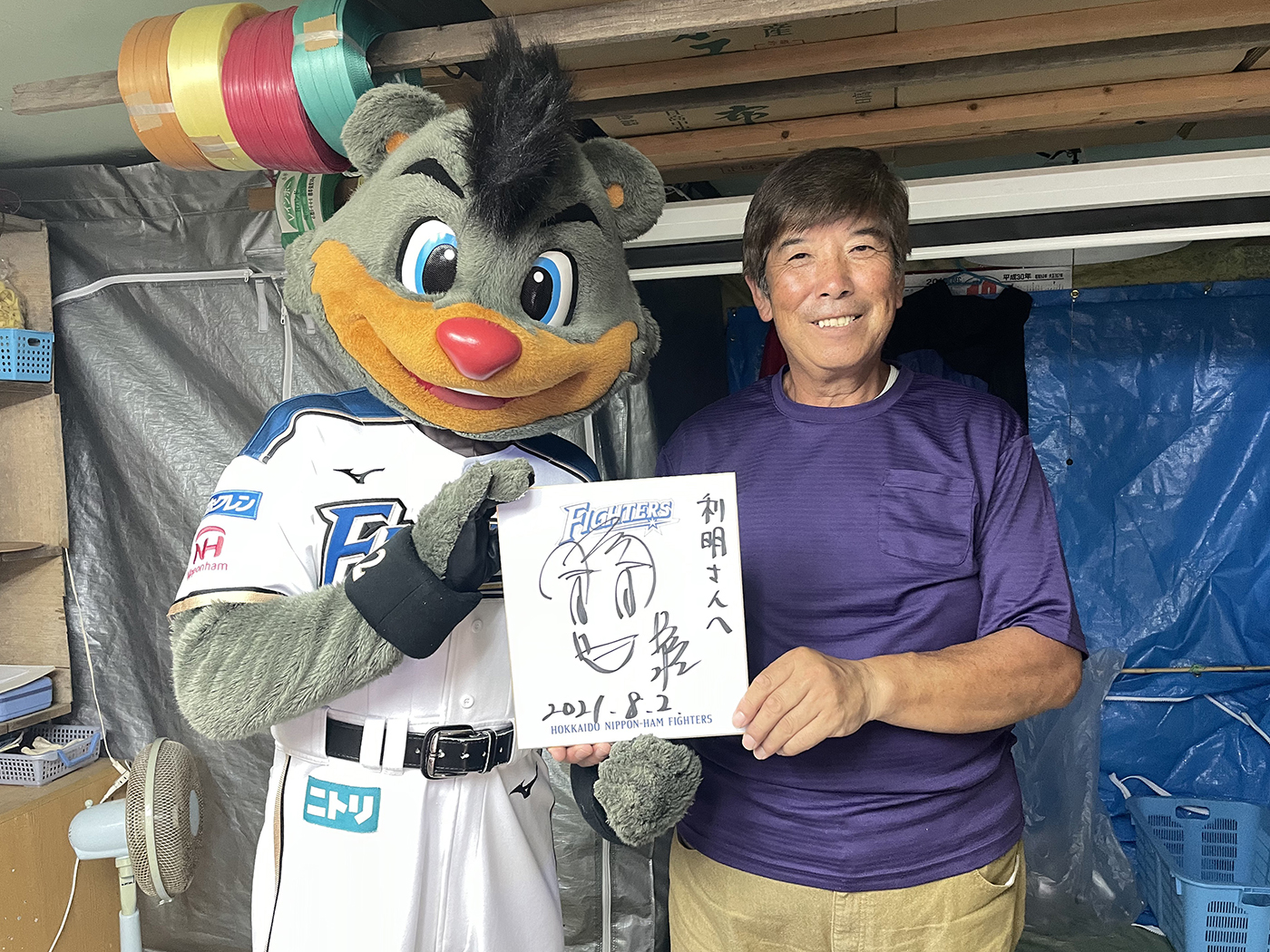 佐藤さん、貴重なお話ありがとうございました
佐藤さん、貴重なお話ありがとうございました![]()
 お土産に昆布たくさんいただいちゃいました
お土産に昆布たくさんいただいちゃいました![]()
コレでしばらくの間ダシに困らない(笑)。
明日は雨予報ですが、またまた
日帰りで浦河に行って来まーす!![]()
![]()




